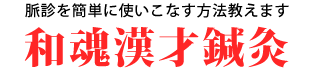インフルエンザの鍼灸治療
2017-02-28
和魂漢才鍼灸の濵田です。
今回はインフルエンザで発熱をしているかたへの治療症例をご紹介します。
インフルエンザなどの発熱症状も、鍼灸治療で正しく治療すれば、スッキリと、より早く治すことができます。
昔の書物を読むと、風邪や発熱などの症状の治療の情報はとてもたくさん紹介されています。
しかし、
今の日本の鍼灸の現状では、風邪症状や熱が出たからといって、鍼灸院に来られる方は残念ながらほとんどいないですね…
だからと言って、風邪や発熱の治療法を勉強する必要がないのか?というとそうではないと思います。
風邪や発熱の治療を理解できると、“ぎっくり腰”などの急性期の痛みの治療にも応用ができます。
その“ぎっくり腰”などの急性期の痛みを治療するときに大切なのは、病位と呼ばれる病の深さになります。
今回は、その病位を意識して治療をおこなったインフルエンザによる発熱の治療をご紹介しますね。
【患者さん情報】
(主訴)
発熱38度6分
寒気
頭痛(特に後頭部)
手足の節々が痛む
昨日から軽い寒気がではじめる。
翌日から発熱・寒気・手足の節々の痛みが発症。
内科にいくとインフルエンザと診断。
リレンザ・解熱剤を処方されるが、飲まないほうが良いと伝える。
【診察情報】
・脉状(浮・緊)
腹診は以下の通り
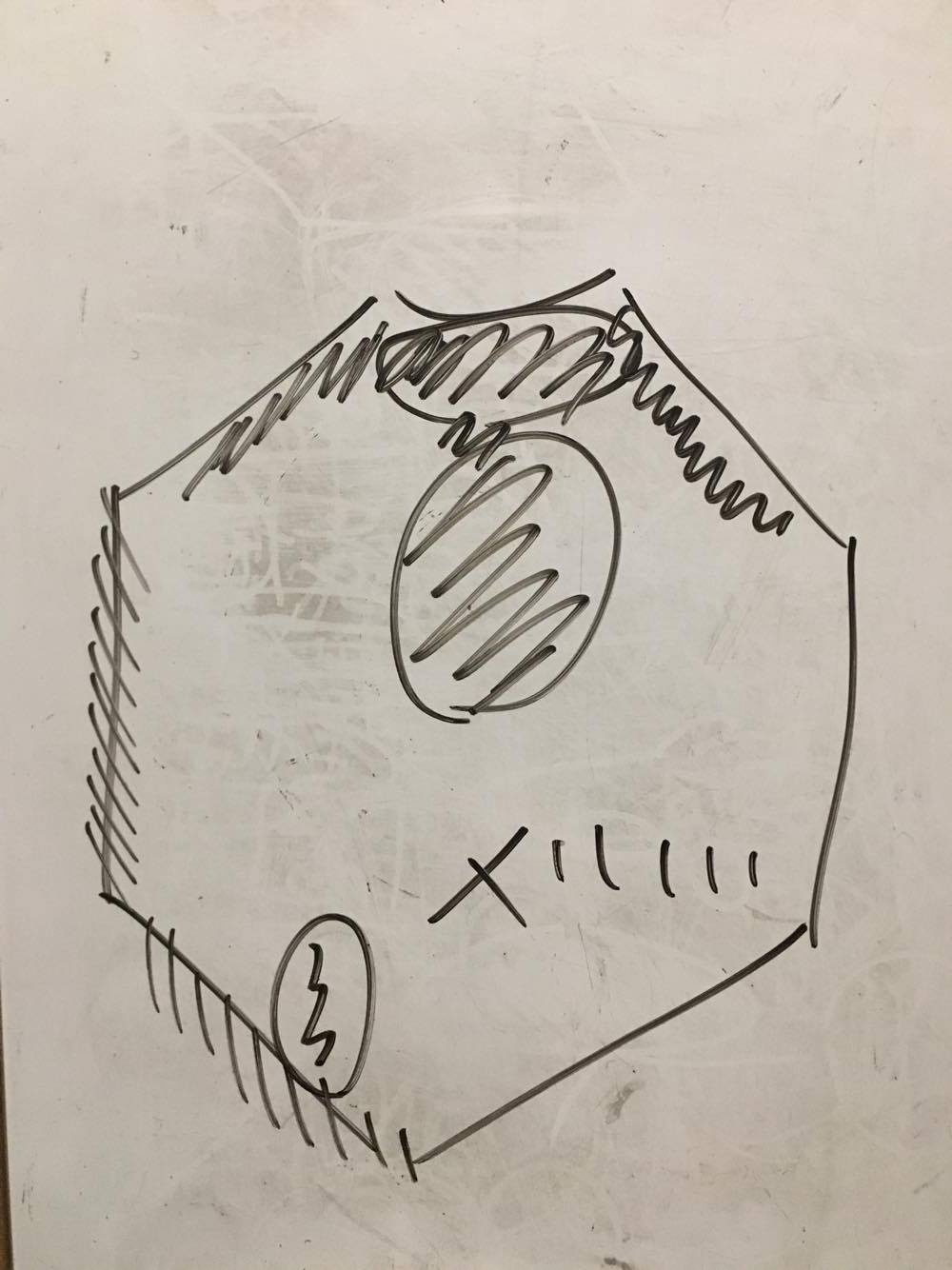
※背中の情報の特記事項としては“無汗”!
【診断】
診察情報より病位は「太陽病」の表実症と判断。
太陽位の“寒邪”を「発汗法」で発散させることを主として治療はすすめる。
【治療】
⑴太陽位の邪をさばく治療から始める。
(うつ伏せ)
・熱の治療のため胸椎の際への刺鍼
三椎下
五椎下
六椎下
七椎下
に対して瀉法。
キュッとしまっていた毛穴が開き、じわっと汗が出始める。
この時点で、節々の痛みは半減とのこと。
「のどのイガイガ」を自覚
・仰向けになって脈の確認
緊脉は解除。
浮脈は落ち着くが、まだ少し残る。
⑵仰向けで手足に刺鍼
右尺沢
右三陰交
のどのイガイガがなくなる。
⑶汗が出過ぎないよう調整するために灸
中脘
左陽池
→浮脉が落ち着いたので治療は終了
水分をとって、着替えて、ゆっくり寝るように伝える。
【経過】
翌日、熱は36度5分まで下がる。
寒気・頭痛は無し。
節々の痛みは1割ほど残る。
インフルエンザと診断されたため、仕事は治療初日から5日間休むが、残り4日は元気に過ごせた。
その後、空咳が少し出ていたため、その治療を1度行う。
【考察】
先程にも述べた通り、今回の治療は病位(病の深さ)を意識して治療を行いました。
脈が浮・悪寒発熱・後頭部の痛みという情報から病位は、太陽病位と判断。
そして、
脈が緊脈だったため、寒邪によって起こった発熱と判断。
(傷寒論条文より)
太陽病、或は発熱し、或はいまだ発熱せず、必ず悪寒、體痛、吐逆、脉が陰陽ともに緊のもの、名を傷寒と為す。
そして、
頭痛・無汗・節々の痛みという情報から太陽病の傷寒の中でも、麻黄湯症として治療は進めました。
(傷寒論の条文より)
太陽病、頭痛・発熱・身疼・腰痛・骨節疼痛。悪風し、汗無く、喘するものは麻黄湯、之を主る。
麻黄湯は、邪が主に太陽経脈にあって、悪寒発熱して無汗という状態に処方する漢方薬になります。
その漢方の作用は「発汗」になります。
僕たち鍼灸師は、漢方薬を処方することはできませんが、傷寒論などの漢方の知識を学ぶことによって、風邪や発熱症状が起きてくる原因やその治療方法を学ぶことが出来ます。
その治療方法(今回でいうと発汗)をおこなうための配穴を考えていくと、自分自身が持っている治療配穴が無限に広がり、対応できる患者さんも広がるのでぜひおすすめですね(^^)
今回は、
病位が太陽病位という情報を基に、まず太陽膀胱経の治療から始めました。
特に、実反応が強かった三椎下・五椎下・六椎下・七椎下(第三胸椎・第五胸椎・第六胸椎・第七胸椎の際)の反応に鍼を行うと、ジワっと汗が出始めたので、太陽膀胱経脈の邪の発散ができたと判断できます。
その後、
「のどのイガイガ」するのは、「表の発散に元気を使ったため」にでてきたと判断できるため、その調整のために手足の経穴(右尺沢、右三陰交)に鍼をしました。
最後の仕上げとして、
発汗させすぎて、瞑眩反応などがでないように中脘と左陽池にお灸をして、浮脈が落ち着いたので、治療は終了!!
【まとめ】
先程も述べたように、今回の治療で僕が一番大事にしたことは、病位(病の深さ)です。
整体治療やマッサージ、手技治療などの西洋医学の治療でも、からだの“どこの深さの問題なのか?”はとても大切になりますね。
たとえば、
膝が痛いといっても、関節の問題なのか?筋肉の問題なのか?
この“からだの深さ”の違いによって、当然ながら治療は異なります。
これと同じく東洋医学の治療でも、病位と呼ばれる病の深さによって、治療は異なってきます。
そして、鍼を打つべき順番も異なってくると思います。
今回の場合は、
発熱初期ということで、太陽病位と呼ばれる浅い深さに邪がいたため、太陽膀胱経から治療をはじめました。
傷寒論などの漢方の知識を学ぶことで、病位とよばれる“病や邪の深さ”を意識して治療するようになり、ヒトのからだを表面的にではなく、より立体的に診察、治療が出来るようになります。
そして、
この病位(病の深さ)を判断するために大切なのは脈診になりますね。
今回の場合、浮脈という情報を基に太陽病と判断して治療しました。
このようにシンプルな脈診情報だけでも、治療の方針を立てるのにとても役に立ちます。
鍼灸師唯一の強みとも言える脈診を使うと、治療ができる患者さんの幅も広がり、配穴にも迷わなくなるのでぜひおすすめですね(^^;
次回は,
病位を意識した“ぎっくり腰”の治療については書いていきたいと思います。
濵田貴之でした。